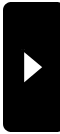2020年09月21日
薪置き場プロジェクト
これも「前庭作りシリーズ」になるのかな?
一昨日に掘り出した木の根だけでは無く、前庭の右端っこには、
栗の木の伐採で出た枝や、台風で落ちた枝が置いてあります。もちろん薪として利用する予定なのですが・・。

今までは先日崩した山が目隠しになっていたので気になりませんでしたが、こうなってくるとどこかへ移動させたくなってきます。
さらに、薪置き場の問題はここだけではありません。
今の薪棚は、単管パイプで組んだものが1つと、その横に野積み状態のものが一つです。
単管パイプで組んだものも、昨年の台風19号で屋根が飛ばされて、やっぱり野積み状態です。

さらに、さらに、この場所は、山側の敷地との境界線に沿って配置していましたので、山側の敷地を併合した今となっては、敷地内に食い込む形となって、将来的に土地の使い勝手を悪くするかもしれません。
なので、この度、「薪置き場プロジェクト」を発動させることにいたしました。
それでは早速ですが、「薪置き場プロジェクト」の概要です。
○フェーズ1
土地の外周の道路沿いに、単管パイプの薪棚を新たに建設します。
そこに現単管パイプ薪棚の薪を移動させます。入りきらなかった分は家の軒下の薪棚へ。
○フェーズ2
空になった現単管パイプ薪棚を解体し、新単管パイプ薪棚の隣へ移築します。当然ながら屋根は直します。
現在野積みになっている薪を移築した薪棚へ移動させます。
これで現在の薪棚の場所はすっきりするはずです。
○フェーズ3
前庭に積んである分も含めて、山側の敷地に散在する薪の元になる木や枝を集めます。
その行き先は・・・。まだ全然考えてません!(^ ^;
フェーズ2が終わった時点で考えます。
それではプロジェクトスタート!
スケジュールを書かないところが、このプロジェクトの最大の問題か・・。
相変わらずの行き当たりばったりでいきます・・。

一昨日に掘り出した木の根だけでは無く、前庭の右端っこには、
栗の木の伐採で出た枝や、台風で落ちた枝が置いてあります。もちろん薪として利用する予定なのですが・・。

今までは先日崩した山が目隠しになっていたので気になりませんでしたが、こうなってくるとどこかへ移動させたくなってきます。
さらに、薪置き場の問題はここだけではありません。
今の薪棚は、単管パイプで組んだものが1つと、その横に野積み状態のものが一つです。
単管パイプで組んだものも、昨年の台風19号で屋根が飛ばされて、やっぱり野積み状態です。

さらに、さらに、この場所は、山側の敷地との境界線に沿って配置していましたので、山側の敷地を併合した今となっては、敷地内に食い込む形となって、将来的に土地の使い勝手を悪くするかもしれません。
なので、この度、「薪置き場プロジェクト」を発動させることにいたしました。
それでは早速ですが、「薪置き場プロジェクト」の概要です。
○フェーズ1
土地の外周の道路沿いに、単管パイプの薪棚を新たに建設します。
そこに現単管パイプ薪棚の薪を移動させます。入りきらなかった分は家の軒下の薪棚へ。
○フェーズ2
空になった現単管パイプ薪棚を解体し、新単管パイプ薪棚の隣へ移築します。当然ながら屋根は直します。
現在野積みになっている薪を移築した薪棚へ移動させます。
これで現在の薪棚の場所はすっきりするはずです。
○フェーズ3
前庭に積んである分も含めて、山側の敷地に散在する薪の元になる木や枝を集めます。
その行き先は・・・。まだ全然考えてません!(^ ^;
フェーズ2が終わった時点で考えます。
それではプロジェクトスタート!
スケジュールを書かないところが、このプロジェクトの最大の問題か・・。
相変わらずの行き当たりばったりでいきます・・。

Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(0)
2020年05月31日
森を作る
前回の投稿からずいぶん間隔が空いてしまいました。
すっかり新緑の季節になってしまいました。

この間にも色々ありましたが、一番大きいのは我が家の敷地面積が増えたことでしょうか。
山側の隣の敷地に、ひょろ長い檜がたくさん立っていて、そのうちの1本が昨年の台風19号で倒れたのは以前に書きました。
http://buc.naganoblog.jp/e2427409.html
残っている木もいつ倒れてくるか分からず、全部刈って欲しいと隣の地主様と交渉していたのですが、結局うちがその土地を買い取って、うちが伐採することになりました。
買い取ると言っても山林ですから、その値段は驚くほど安い。
これで、元の土地に今回の472m2を加えて、合計の敷地面積は2000m2を超えました。
そして、今週、林業士の金井さんにお願いして伐採を行いました。
今回購入した土地の木をほぼ全て伐採してしまいます。
木曜日に伐採、金曜日に搬出。
枝はチップにしてもらいます。

さてさて、ここまでが前置き。
裏の山側は雑木林にしたいと以前書いていました。
http://buc.naganoblog.jp/e2230231.html
でもどうすれば雑木林にすることができるのか全く分かりませんでした。
木を買って植えて育てるの?
分からなかったので、去年の草刈りは、刈分けると言っていながら、刈払機を振り回してがむしゃらに刈っていました。
http://buc.naganoblog.jp/e2400157.html
こんなのでは雑木林になるはずもありません。
そして今年・・。
今回の伐採の打ち合わせの中で、金井さんから、「一緒に刈って雑木林を作りませんか」と、とてもありがたいお言葉が。
そして今回、伐採の手空き時間で、「雑木林作り」を教わることができました。
基本的な考え方は、一定のエリア内(とりあえず2m2ぐらい?)で残したい木を選びます。
そしてそれ以外の木を全て刈ってしまいます。
株立ちしている木も多いのですが、良さそうな枝を残して残りは剪定します。
要するにそのエリアで大きくする木を1本だけにするということです。。
その木が大きくなると日陰ができて雑草や他の木が生えにくくなって・・。やがて雑木林に。
それからやっぱり大事なのは木の種類を知ること。
今回、金井さんに教えてもらって、樹種が見分けられるようになってきました。
うちの敷地に生えているのは、クリ、ウルシ、サクラ、クルミ、ウリカエデ、コシアブラ、イロハモミジ、ダンコウバイ、アオダモ、ウワミズザクラ、ツゲ、ヤマアジサイ、ヤマツツジ、サワラ、イタヤカエデ、ハギ、フジなどなど。
とりあえず樹木を買う必要は全くありません。
木の名前が分かると、残したい木を選ぶ時に、バランス良く選べるようになります。
ただしウルシとフジは残さない方が良いようです。
最初のうちは残すと選んだ木には目印と名前を書いておきます。
そしてそれ以外の木や草を刈っていく。

書くだけなら簡単ですが、すでに木も草もかなり生い茂っており、鎌とノコギリと剪定ばさみでの手作業での刈払い作業です。
大雑把になってしまう刈払機は使えません。
茂みの中に入り込んで、草を刈りながら、幹の位置を確認し、残さない物はできるだけ根に近い位置で切っていきます。
株立ちの木は、できるだけ上にまっすぐ伸びている物を選んで、他は根元で切っていきます。
なかなかに重労働です。
しかしそうして整理していくと、不思議と雑木林のイメージが見えてきます。
何故かとても嬉しくなってきます。「森を作っているんだなぁ」と。


去年までは草木とがむしゃらに「闘って」いました。
今は「共生する」ということがちょっとだけ分かった気がします。
これはとても貴重な体験。
とてもありがたいです。

新たな土地からの写真です。
すっかり新緑の季節になってしまいました。

この間にも色々ありましたが、一番大きいのは我が家の敷地面積が増えたことでしょうか。
山側の隣の敷地に、ひょろ長い檜がたくさん立っていて、そのうちの1本が昨年の台風19号で倒れたのは以前に書きました。
http://buc.naganoblog.jp/e2427409.html
残っている木もいつ倒れてくるか分からず、全部刈って欲しいと隣の地主様と交渉していたのですが、結局うちがその土地を買い取って、うちが伐採することになりました。
買い取ると言っても山林ですから、その値段は驚くほど安い。
これで、元の土地に今回の472m2を加えて、合計の敷地面積は2000m2を超えました。
そして、今週、林業士の金井さんにお願いして伐採を行いました。
今回購入した土地の木をほぼ全て伐採してしまいます。
木曜日に伐採、金曜日に搬出。
枝はチップにしてもらいます。

さてさて、ここまでが前置き。
裏の山側は雑木林にしたいと以前書いていました。
http://buc.naganoblog.jp/e2230231.html
でもどうすれば雑木林にすることができるのか全く分かりませんでした。
木を買って植えて育てるの?
分からなかったので、去年の草刈りは、刈分けると言っていながら、刈払機を振り回してがむしゃらに刈っていました。
http://buc.naganoblog.jp/e2400157.html
こんなのでは雑木林になるはずもありません。
そして今年・・。
今回の伐採の打ち合わせの中で、金井さんから、「一緒に刈って雑木林を作りませんか」と、とてもありがたいお言葉が。
そして今回、伐採の手空き時間で、「雑木林作り」を教わることができました。
基本的な考え方は、一定のエリア内(とりあえず2m2ぐらい?)で残したい木を選びます。
そしてそれ以外の木を全て刈ってしまいます。
株立ちしている木も多いのですが、良さそうな枝を残して残りは剪定します。
要するにそのエリアで大きくする木を1本だけにするということです。。
その木が大きくなると日陰ができて雑草や他の木が生えにくくなって・・。やがて雑木林に。
それからやっぱり大事なのは木の種類を知ること。
今回、金井さんに教えてもらって、樹種が見分けられるようになってきました。
うちの敷地に生えているのは、クリ、ウルシ、サクラ、クルミ、ウリカエデ、コシアブラ、イロハモミジ、ダンコウバイ、アオダモ、ウワミズザクラ、ツゲ、ヤマアジサイ、ヤマツツジ、サワラ、イタヤカエデ、ハギ、フジなどなど。
とりあえず樹木を買う必要は全くありません。
木の名前が分かると、残したい木を選ぶ時に、バランス良く選べるようになります。
ただしウルシとフジは残さない方が良いようです。
最初のうちは残すと選んだ木には目印と名前を書いておきます。
そしてそれ以外の木や草を刈っていく。

書くだけなら簡単ですが、すでに木も草もかなり生い茂っており、鎌とノコギリと剪定ばさみでの手作業での刈払い作業です。
大雑把になってしまう刈払機は使えません。
茂みの中に入り込んで、草を刈りながら、幹の位置を確認し、残さない物はできるだけ根に近い位置で切っていきます。
株立ちの木は、できるだけ上にまっすぐ伸びている物を選んで、他は根元で切っていきます。
なかなかに重労働です。
しかしそうして整理していくと、不思議と雑木林のイメージが見えてきます。
何故かとても嬉しくなってきます。「森を作っているんだなぁ」と。


去年までは草木とがむしゃらに「闘って」いました。
今は「共生する」ということがちょっとだけ分かった気がします。
これはとても貴重な体験。
とてもありがたいです。

新たな土地からの写真です。
Posted by ぶっち at
18:08
│Comments(0)
2020年04月07日
栗の木散髪
我が家のシンボルツリーの大きな栗の木。
一昨年、昨年と台風が襲来。
今までは林の中で大きく生長していた栗も、伐採で周囲に木が無くなったことで、大風の影響をもろに受け、枝がたくさん折れて落下。
落下せずに引っかかったりぶら下がったりしているのも有ります。
http://buc.naganoblog.jp/e2303914.html
http://buc.naganoblog.jp/e2427409.html
そして、また台風が来ると折れるであろう枝が残っています。
なので、栗の木の散髪を行うことにしました。

とは言ってもこの大木、私ではとても手も足も出ません。
なのでこの土地の伐採をお願いした、林業士の金井さんにお願いすることにしました。
さすがこの道のプロ。ロープを使い身軽に木の上に登られます。

折れた木を除去して切り口を綺麗に。
伸びすぎた木は短くして、これ以上折れないように。
昼過ぎまでの作業で栗の木はとてもすっきりしました。
ありがとうございました。

落とした枝も整理して頂きましたが、
それでもこれだけ残っています。


また仕事がたくさんできました・・(嬉)。

一昨年、昨年と台風が襲来。
今までは林の中で大きく生長していた栗も、伐採で周囲に木が無くなったことで、大風の影響をもろに受け、枝がたくさん折れて落下。
落下せずに引っかかったりぶら下がったりしているのも有ります。
http://buc.naganoblog.jp/e2303914.html
http://buc.naganoblog.jp/e2427409.html
そして、また台風が来ると折れるであろう枝が残っています。
なので、栗の木の散髪を行うことにしました。

とは言ってもこの大木、私ではとても手も足も出ません。
なのでこの土地の伐採をお願いした、林業士の金井さんにお願いすることにしました。
さすがこの道のプロ。ロープを使い身軽に木の上に登られます。

折れた木を除去して切り口を綺麗に。
伸びすぎた木は短くして、これ以上折れないように。
昼過ぎまでの作業で栗の木はとてもすっきりしました。
ありがとうございました。

落とした枝も整理して頂きましたが、
それでもこれだけ残っています。


また仕事がたくさんできました・・(嬉)。

Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(0)
2020年03月23日
ウッドチッパー
庭の枝をチップにして撒きたい!
長い間迷っていましたが、ついに買ってしまいました。「ウッドチッパー」を。
ウッドチッパーはガーデンシュレッダーとも呼ばれますが、色々な方式があります。
まずは駆動方法、電動とエンジンがあります。
電動は安くて軽いけど非力で、エンジン式は総じてパワフル。けど高くて重い。
我が家で出てくる枝の量と効率を考えると、やっぱりエンジンを選びたい。
また粉砕方式の違いで、ギア式とディスク式があって、ギア式はチップ大きめで刃の交換不要。
ディスク式はチップ細かく、素早く粉砕できるらしい。土に撒いて処分することを考えると、ディスク式の方が良いかな。
エンジン方式の物はディスク式が多いような感じです。
値段的にも、エンジン式の物は本当にピンからキリで、10万円以下で買える中国製の怪しげな物から、自走する何百万円の物まで。
やっぱり、こういう負荷のかかる機械に故障はつきものなので、ここはできるだけ信頼性の高い物を選びたい。
かといってお値段もできるだけ安く済ませたい。
色々悩んだ結果、最終的に選んだのは、共立のマルチチッパーKC40A
やっぱりホンダGX160エンジンの信頼性と、サービスパーツの入手性と、故障しても近所の店で修理対応できるということが決め手となりました。
KC40Aは、まだ、カタログには載ってませんが、従来のKC40が安全スイッチ付きにモデルチェンジされたものです。
KC40のうたい文句は、「独自のスパイラル刃採用でマルチに切断。刈草・ツル・ワラ等チッパーでは苦手な柔らかい材質のものも切断可能です。」とのこと。
最大処理径は40mmで処理能力は0.8m3/h。 最大出力3.6 kW。

実際に使ってみます。
おっ、ぐいぐいと枝を引っ張って飲み込んで行ってくれます。
KC40の良いところは切断用の駆動とは別に、枝を引き込むための駆動があることです。
通常のディスク式は押し込むことが必要なようですが、これはそんな手間は必要ありません。
また、太めの枝だと枝も真っ直ぐに選定しなければ機械に入れることができない物も多いようですが、これは少々枝が張っていてもパワフルに飲み込んで行ってくれます。
凄く作業効率が良いです。積んであった枝が見る見る無くなっていきます。
ただし弱点もあります。
それは切断したチップの細かさ。
太い枝を細かくするのは苦手なようで、大きめに切断されます。
ギア式の切断サイズと同様でしょうか。
腐葉土にはできそうも無いサイズで、通路に撒くのに良さそうなサイズです。
細い枝やつる、葉っぱは結構細かく砕いてくれます。

あと使用上の注意点ですが、太い枝を飲み込む時に、破断した時の加減により、大きめの枝が投入口から勢いよく飛び出してきます。
なので保護メガネの着用は必須です。
全体的には枝の処理がはかどって大満足です。
長い間迷っていましたが、ついに買ってしまいました。「ウッドチッパー」を。
ウッドチッパーはガーデンシュレッダーとも呼ばれますが、色々な方式があります。
まずは駆動方法、電動とエンジンがあります。
電動は安くて軽いけど非力で、エンジン式は総じてパワフル。けど高くて重い。
我が家で出てくる枝の量と効率を考えると、やっぱりエンジンを選びたい。
また粉砕方式の違いで、ギア式とディスク式があって、ギア式はチップ大きめで刃の交換不要。
ディスク式はチップ細かく、素早く粉砕できるらしい。土に撒いて処分することを考えると、ディスク式の方が良いかな。
エンジン方式の物はディスク式が多いような感じです。
値段的にも、エンジン式の物は本当にピンからキリで、10万円以下で買える中国製の怪しげな物から、自走する何百万円の物まで。
やっぱり、こういう負荷のかかる機械に故障はつきものなので、ここはできるだけ信頼性の高い物を選びたい。
かといってお値段もできるだけ安く済ませたい。
色々悩んだ結果、最終的に選んだのは、共立のマルチチッパーKC40A
やっぱりホンダGX160エンジンの信頼性と、サービスパーツの入手性と、故障しても近所の店で修理対応できるということが決め手となりました。
KC40Aは、まだ、カタログには載ってませんが、従来のKC40が安全スイッチ付きにモデルチェンジされたものです。
KC40のうたい文句は、「独自のスパイラル刃採用でマルチに切断。刈草・ツル・ワラ等チッパーでは苦手な柔らかい材質のものも切断可能です。」とのこと。
最大処理径は40mmで処理能力は0.8m3/h。 最大出力3.6 kW。

実際に使ってみます。
おっ、ぐいぐいと枝を引っ張って飲み込んで行ってくれます。
KC40の良いところは切断用の駆動とは別に、枝を引き込むための駆動があることです。
通常のディスク式は押し込むことが必要なようですが、これはそんな手間は必要ありません。
また、太めの枝だと枝も真っ直ぐに選定しなければ機械に入れることができない物も多いようですが、これは少々枝が張っていてもパワフルに飲み込んで行ってくれます。
凄く作業効率が良いです。積んであった枝が見る見る無くなっていきます。
ただし弱点もあります。
それは切断したチップの細かさ。
太い枝を細かくするのは苦手なようで、大きめに切断されます。
ギア式の切断サイズと同様でしょうか。
腐葉土にはできそうも無いサイズで、通路に撒くのに良さそうなサイズです。
細い枝やつる、葉っぱは結構細かく砕いてくれます。

あと使用上の注意点ですが、太い枝を飲み込む時に、破断した時の加減により、大きめの枝が投入口から勢いよく飛び出してきます。
なので保護メガネの着用は必須です。
全体的には枝の処理がはかどって大満足です。
Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(1)
2020年02月23日
大きな栗の木の下を・・。
おととし9月の台風21号、去年10月の台風19号。
この二つの台風で、うちの大きな栗の木の枝はたくさん折れて落下してきました。
おととし9月の台風21号の分は枝打ちだけは行っていたのですが、
綺麗にするまでには至っておりませんでした。
去年10月の台風19号の分はそのまま放置・・。
なので栗の木の下は枝が重なり合って、綺麗な状態ではありません。

ここを雑草が生える前になんとかしたい!
なのでなんとかしましょう!
というわけで、チェーンソーを持ち出して作業開始。
枝と木を分けて、木は薪で使えるサイズにカットしていきます。

去年の枯れ雑草に埋まってしまった物やら、土に埋まってしまっている物などを掘り起こし、苦労しながら、なんとか整理完了。
結構な量で、こんな山が3つできてしまいました。

薪になる分は良いとしても、枝はどうしようかなぁ。
やっぱり枝を粉々にしてくれるガーデンシュレッダー要るよなぁ。
前から欲しかったんだよなぁ。
とにかくも栗の木の下はずいぶん整理できました。

あと、大きな切り株がまだ転がっているので、
次はこれをどうにかしたいです・・。

この二つの台風で、うちの大きな栗の木の枝はたくさん折れて落下してきました。
おととし9月の台風21号の分は枝打ちだけは行っていたのですが、
綺麗にするまでには至っておりませんでした。
去年10月の台風19号の分はそのまま放置・・。
なので栗の木の下は枝が重なり合って、綺麗な状態ではありません。

ここを雑草が生える前になんとかしたい!
なのでなんとかしましょう!
というわけで、チェーンソーを持ち出して作業開始。
枝と木を分けて、木は薪で使えるサイズにカットしていきます。
去年の枯れ雑草に埋まってしまった物やら、土に埋まってしまっている物などを掘り起こし、苦労しながら、なんとか整理完了。
結構な量で、こんな山が3つできてしまいました。

薪になる分は良いとしても、枝はどうしようかなぁ。
やっぱり枝を粉々にしてくれるガーデンシュレッダー要るよなぁ。
前から欲しかったんだよなぁ。
とにかくも栗の木の下はずいぶん整理できました。

あと、大きな切り株がまだ転がっているので、
次はこれをどうにかしたいです・・。

Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(0)
2019年08月14日
除草剤
8/3,4も伊那に居たのですが、雑草との格闘以外めぼしいことも無く・・。
8/10-12の3連休は盆の行事と仕事で潰れ、今日から盆休みとなります。
で、今日も朝から雑草と格闘しています。
もうツタ植物や、残っている切り株から生えてくる木の芽の勢いには対抗しようがありません。
なので、先日から一部で導入したのが「除草剤」。
できるだけ土を痛めたくなかったので、農耕地用で、かつ有名どころということで、「ラウンドアップマックスロード」をとりあえず買ってみました。
・・・・値段にびびりながら。
なんか他のものと比べても段違いに高い。

どこにでも撒くわけではありませんが、1リットルなんてすぐ無くなってしまう。
このままではお財布が持ちません。
と言うわけで調べてみました。
除草剤って農耕地用と非農耕地用がありますが、農耕地用というのは農林水産省に登録されたものと言うことで、内容が一緒であっても、登録にかかる費用や手間がかかるので、その分お高くなるようですね。
さらに「ラウンドアップマックスロード」の有効成分はグリホサートと言うものですが、これは土に落ちると分解され無害化するという特徴が有って、他にそのような優れた製品も無かったので、その特許を持っていたモンサントと言う会社が「ラウンドアップ」で市場を席巻したというところでしょうか。
しかし、その特許も今は切れているようで、ジェネリック薬品のように、グリホサート成分を使用した製品も多く出回ってきているようです。
それだけ分ければ十分。
今日、綿半で改めて見てみました。
確かにジェネリック品、色々あります。
今回買ったのは、エイトアップというもので、農耕地用でお値段なんとラウンドアップマックスロードの1/3。
ジェネリック品は効きが遅いという話もありますが、この値段差には代えられんわなぁ。

グリホサートは発がん性があるとか、耐性雑草が増えてるとか、現代農業がこのグリホサートへの依存が大きいとか・・。
色々勉強になりました。
8/10-12の3連休は盆の行事と仕事で潰れ、今日から盆休みとなります。
で、今日も朝から雑草と格闘しています。
もうツタ植物や、残っている切り株から生えてくる木の芽の勢いには対抗しようがありません。
なので、先日から一部で導入したのが「除草剤」。
できるだけ土を痛めたくなかったので、農耕地用で、かつ有名どころということで、「ラウンドアップマックスロード」をとりあえず買ってみました。
・・・・値段にびびりながら。
なんか他のものと比べても段違いに高い。

どこにでも撒くわけではありませんが、1リットルなんてすぐ無くなってしまう。
このままではお財布が持ちません。
と言うわけで調べてみました。
除草剤って農耕地用と非農耕地用がありますが、農耕地用というのは農林水産省に登録されたものと言うことで、内容が一緒であっても、登録にかかる費用や手間がかかるので、その分お高くなるようですね。
さらに「ラウンドアップマックスロード」の有効成分はグリホサートと言うものですが、これは土に落ちると分解され無害化するという特徴が有って、他にそのような優れた製品も無かったので、その特許を持っていたモンサントと言う会社が「ラウンドアップ」で市場を席巻したというところでしょうか。
しかし、その特許も今は切れているようで、ジェネリック薬品のように、グリホサート成分を使用した製品も多く出回ってきているようです。
それだけ分ければ十分。
今日、綿半で改めて見てみました。
確かにジェネリック品、色々あります。
今回買ったのは、エイトアップというもので、農耕地用でお値段なんとラウンドアップマックスロードの1/3。
ジェネリック品は効きが遅いという話もありますが、この値段差には代えられんわなぁ。

グリホサートは発がん性があるとか、耐性雑草が増えてるとか、現代農業がこのグリホサートへの依存が大きいとか・・。
色々勉強になりました。
Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(0)
2019年07月13日
廃材を燃やしたり
今日の天気予報では、夜まで雨が降らないらしい。
なので、やれることをやりましょう。
まず廃材を燃やします。
何故か敷地では家の建築とは関係ない廃材が発掘されたり、薪としては使えない木が転がっていたりします。
天気が良いうちに燃やしてしまいましょう。
朝は風も無くて良い感じです。
野焼きはダメなので焼却炉を使いましょう。
焼却炉はうまく空気が抜けるので、あっという間に燃やせてしまいました。

その後は製品評価をしたり、栗の木の下に置いてあった堆肥枠を補修して、家の裏に移動させたり。
ホームセンターに補修用の材料を買いに行ったりすると、あっという間に時間が過ぎていきます。

昼はせっかくなので、ウッドデッキで。
やっぱり気持ちいいです。

とか言ってると3時頃からぽつぽつと雨が。
あれま。天気予報当たりません。
その後も雨はほぼ止むことも無く・・。
梅雨なので仕方ないです・・。
なので、やれることをやりましょう。
まず廃材を燃やします。
何故か敷地では家の建築とは関係ない廃材が発掘されたり、薪としては使えない木が転がっていたりします。
天気が良いうちに燃やしてしまいましょう。
朝は風も無くて良い感じです。
野焼きはダメなので焼却炉を使いましょう。
焼却炉はうまく空気が抜けるので、あっという間に燃やせてしまいました。

その後は製品評価をしたり、栗の木の下に置いてあった堆肥枠を補修して、家の裏に移動させたり。
ホームセンターに補修用の材料を買いに行ったりすると、あっという間に時間が過ぎていきます。

昼はせっかくなので、ウッドデッキで。
やっぱり気持ちいいです。

とか言ってると3時頃からぽつぽつと雨が。
あれま。天気予報当たりません。
その後も雨はほぼ止むことも無く・・。
梅雨なので仕方ないです・・。
Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(0)
2019年07月06日
草刈り!
雨続きなので1週飛ばしてしまいました。
今週末は曇り予報で、一安心。
まず、びっくりしたのが・・。
駐車しておいた軽自動車を移動させると、その下にはきのこがびっしり。
早速食べ・・ない方が良いでしょうね。

あと、裏の法面の下部の土がえぐれて土が流れ出している!
どうやら樋が詰まってオーバーフローしたようです。
樋の様子を後で確認しましょう。
それと雑草。
今シーズン、敷地は手つかずでしたが、そのせいでもう一部は背丈より伸びてジャングル状態。
まずはこの対策ですね。
この土地を入手して初めての頃は、とりあえず何でもかんでも刈っていましたが、
ほんのちょっとだけ草木も分かるようになりましたので、刈り分けることにします。
今回の方針。
・雑草に埋もれている山ツツジ、山あじさいを発掘して残す。
・花の咲いている草木は残す。
・とげのある木、ツタのような絡まる雑草は徹底排除。
・それ以外は基本的に切るが、目隠しになるような木は残す。
では作業開始です。

方針は立ててみましたが、実際刈るのは大変。
まず、草が何重にも重なって、もう生え際が見えない。
上から順々に刈っていきますがとても手間がかかる。
そしてツタのような草が多い。
草刈り機に絡まって、腹が立つ。
「んがーっ」てなって草刈り機を振り回したくなる。
さらに根の部分がちゃんと見えないので、刈ったつもりでも刈り残しがやっぱり多い。
これは何回にも分けてやらなければ仕方ないですね・・。

これでも一応刈った後・・。
今週末は曇り予報で、一安心。
まず、びっくりしたのが・・。
駐車しておいた軽自動車を移動させると、その下にはきのこがびっしり。
早速食べ・・ない方が良いでしょうね。

あと、裏の法面の下部の土がえぐれて土が流れ出している!
どうやら樋が詰まってオーバーフローしたようです。
樋の様子を後で確認しましょう。
それと雑草。
今シーズン、敷地は手つかずでしたが、そのせいでもう一部は背丈より伸びてジャングル状態。
まずはこの対策ですね。
この土地を入手して初めての頃は、とりあえず何でもかんでも刈っていましたが、
ほんのちょっとだけ草木も分かるようになりましたので、刈り分けることにします。
今回の方針。
・雑草に埋もれている山ツツジ、山あじさいを発掘して残す。
・花の咲いている草木は残す。
・とげのある木、ツタのような絡まる雑草は徹底排除。
・それ以外は基本的に切るが、目隠しになるような木は残す。
では作業開始です。

方針は立ててみましたが、実際刈るのは大変。
まず、草が何重にも重なって、もう生え際が見えない。
上から順々に刈っていきますがとても手間がかかる。
そしてツタのような草が多い。
草刈り機に絡まって、腹が立つ。
「んがーっ」てなって草刈り機を振り回したくなる。
さらに根の部分がちゃんと見えないので、刈ったつもりでも刈り残しがやっぱり多い。
これは何回にも分けてやらなければ仕方ないですね・・。

これでも一応刈った後・・。
Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(0)
2019年06月01日
空へ続く北ウイング
伊那の家の東側には県の貯水池があって、その貯水池と家の間には道路のようになっている土地があります。
家に着いてふとその通路のような土地を見てみると、雑草がぼうぼう。
うちの敷地側からも盛大に伸びているので、放っておくわけにはいきません。
ちなみに敷地内はぶっち嫁がまめに草取りしてくれているので、まぁまぁ落ち着いた状態です。
久しぶりに、草刈り機を取り出して・・。重っ!。こんな重かったっけ。

小一時間ほどかけて、草刈り終了。
まぁまぁ綺麗になりました。
またすぐ伸びるんでしょうけど。

続いてウッドデッキ製作作業の続き。
山側のウッドデッキ、名付けて「南ウイング」か入口側のウッドデッキ、名付けて「北ウイング」か。
どちらを先にしようか・・。
縁側のような腰掛け場所が欲しいので、「北ウイング」からにしましょう。
作業初めてすぐに荷物が・・。
まず届いたのは、ニトリからロールブラインド。
ウッドデッキの日よけ用です。
屋外用ではないので、雨天時には使えませんが、安くて場所とらなくて・・。
京都の家でも同様にしていて、屋内用は屋外ではすぐダメになるかと思っていました。
しかし、かれこれもう10年以上経ってますが、全然大丈夫です。
なので、今回も採用!
軒に取り付けたらこんな感じ。

広げたらこんな感じ。

これで日よけもできたので、日差しがきつくてもウッドデッキが使えそうです。
ただこの土地は少し風が強いので、その対策は必要かな。
そしてまたもや荷物が・・。
次は横須賀の元地主様から大きなアジと、ドクダミ草が。
ありがとうございます。
アジはお刺身で頂きます。ドクダミ草はぶっち嫁が植えてくれました。

さて「北ウイング」作りを続けましょう。
とりあえず夕方には板をすべて張り終えました。

そして、ジグソーを使って端部をなだらかな曲線になるように切っていきます。
出来上がったらこんな感じ。

「北ウイング」は縁側のように使いたいので、わんこ落下防止板は取り付けません。
そしてここはウッドデッキの中でも南アルプスが一番よく見渡せて、一番景色が良い場所です。
寝そべってみると、山から空へ続いていく飛行甲板のようです。

とても良い感じです。
家に着いてふとその通路のような土地を見てみると、雑草がぼうぼう。
うちの敷地側からも盛大に伸びているので、放っておくわけにはいきません。
ちなみに敷地内はぶっち嫁がまめに草取りしてくれているので、まぁまぁ落ち着いた状態です。
久しぶりに、草刈り機を取り出して・・。重っ!。こんな重かったっけ。

小一時間ほどかけて、草刈り終了。
まぁまぁ綺麗になりました。
またすぐ伸びるんでしょうけど。

続いてウッドデッキ製作作業の続き。
山側のウッドデッキ、名付けて「南ウイング」か入口側のウッドデッキ、名付けて「北ウイング」か。
どちらを先にしようか・・。
縁側のような腰掛け場所が欲しいので、「北ウイング」からにしましょう。
作業初めてすぐに荷物が・・。
まず届いたのは、ニトリからロールブラインド。
ウッドデッキの日よけ用です。
屋外用ではないので、雨天時には使えませんが、安くて場所とらなくて・・。
京都の家でも同様にしていて、屋内用は屋外ではすぐダメになるかと思っていました。
しかし、かれこれもう10年以上経ってますが、全然大丈夫です。
なので、今回も採用!
軒に取り付けたらこんな感じ。

広げたらこんな感じ。

これで日よけもできたので、日差しがきつくてもウッドデッキが使えそうです。
ただこの土地は少し風が強いので、その対策は必要かな。
そしてまたもや荷物が・・。
次は横須賀の元地主様から大きなアジと、ドクダミ草が。
ありがとうございます。
アジはお刺身で頂きます。ドクダミ草はぶっち嫁が植えてくれました。

さて「北ウイング」作りを続けましょう。
とりあえず夕方には板をすべて張り終えました。

そして、ジグソーを使って端部をなだらかな曲線になるように切っていきます。
出来上がったらこんな感じ。

「北ウイング」は縁側のように使いたいので、わんこ落下防止板は取り付けません。
そしてここはウッドデッキの中でも南アルプスが一番よく見渡せて、一番景色が良い場所です。
寝そべってみると、山から空へ続いていく飛行甲板のようです。

とても良い感じです。
Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(0)
2018年12月08日
今後の予定
今週末も予報では良い天気になりそうですが、第一級の寒波がやってくるということで、寒さは覚悟する必要があるみたいです。
到着して1番の作業は、裏の犬走りのところに設置するシンクを組み立てること。
これは難しい作業ではありません。良い感じに収まりました。
立水栓の位置もバッチリの位置に設置して貰えていました。
ありがとうございます。

ちなみに犬走りには先週入荷した雨水タンクが仮で置かれています。
容量500L。なかなかの大きさです。

その後は富澤さんと定例ミーティング。
今後の予定などを聞いてみましたが、大工工事はあと2週間ぐらいとのこと。
その後、屋内の漆喰塗りができるようになりますが、実際に塗れるのは年末年始になりそうです。
その前に左官の湯澤師匠に教えを請わなければなりませんから、湯澤さんの都合次第になりそうです。
年末は伊那へは行けないと思いますが、暖房は動かせるようにしておいて頂けるようです。
年始は1/4,5,6ぐらいは作業したいな。
完了検査をどの時点で受けるかですが、可能ならば年内にということで。
あと、設備関係の仕上げもありますし、薪ストーブ周りの造作もしなければなりませんし、最終的な引き渡しは1月下旬ぐらいになるのでしょうか。
その後、タイヤを交換しに「ISC」へ行きます。
「ISC」とは「伊那サテライトセンター」の略です。
「伊那市創業支援センター」が12/7から民営化され、名称も変更されました。

ということで、冬タイヤを保管してある「ISC」にてタイヤ交換です。
自分でやるのは春に続いて2回目ですが、フロアジャッキとインパクトレンチとトルクレンチの3点セットで比較的スムーズに作業を終えました。
明日は軽トラックのタイヤを交換しましょう。
今日はまだ日差しがありますので、昼からはまたまた栗の枝の皮剥き。何本目だ?
今度は玄関脇のポーチライト用です。
台風で折れた栗の枝のうち、そこそこの太さで、そこそこの長さのものがもう無いので、少し短いものになってしまいました。

栗の枝は荒皮が厚いので、結構剥くのがめんどくさいです。
ヒノキの皮は結構簡単にぺろんと剥けたんですけど。
素人なりに、分かったことは、栗の皮は繊維方向に剥くより周方向の方が剥きやすそうなので、まず繊維方向に沿って筋のように剥いていきます。この時先端側から根元側の方へ剥いた方が若干ですが剥きやすそうに感じます。
筋のように剥いた後は円周方向に直角に剥いていきます。
そうすれば比較的簡単に向けます。

これで荒皮は剥けるのですが、さらに薄皮があるようです。この薄皮は空気に触れると?茶色く変色して見た目が汚くなりますし、これがまた剥きにくい。オービタルサンダーで磨いていく必要がありますが、剥きたては湿気ているので?綺麗に磨けません。しばらくおいてから磨いた方が良いようです。
以上他に栗を剥く人が居るとも思えませんが、自分への備忘録として・・。
夕方が訪れ、今日も良い感じに山が赤く染まります。

日が陰ってとても寒くなってきました。
今晩は冷え込みそうです。
到着して1番の作業は、裏の犬走りのところに設置するシンクを組み立てること。
これは難しい作業ではありません。良い感じに収まりました。
立水栓の位置もバッチリの位置に設置して貰えていました。
ありがとうございます。

ちなみに犬走りには先週入荷した雨水タンクが仮で置かれています。
容量500L。なかなかの大きさです。

その後は富澤さんと定例ミーティング。
今後の予定などを聞いてみましたが、大工工事はあと2週間ぐらいとのこと。
その後、屋内の漆喰塗りができるようになりますが、実際に塗れるのは年末年始になりそうです。
その前に左官の湯澤師匠に教えを請わなければなりませんから、湯澤さんの都合次第になりそうです。
年末は伊那へは行けないと思いますが、暖房は動かせるようにしておいて頂けるようです。
年始は1/4,5,6ぐらいは作業したいな。
完了検査をどの時点で受けるかですが、可能ならば年内にということで。
あと、設備関係の仕上げもありますし、薪ストーブ周りの造作もしなければなりませんし、最終的な引き渡しは1月下旬ぐらいになるのでしょうか。
その後、タイヤを交換しに「ISC」へ行きます。
「ISC」とは「伊那サテライトセンター」の略です。
「伊那市創業支援センター」が12/7から民営化され、名称も変更されました。

ということで、冬タイヤを保管してある「ISC」にてタイヤ交換です。
自分でやるのは春に続いて2回目ですが、フロアジャッキとインパクトレンチとトルクレンチの3点セットで比較的スムーズに作業を終えました。
明日は軽トラックのタイヤを交換しましょう。
今日はまだ日差しがありますので、昼からはまたまた栗の枝の皮剥き。何本目だ?
今度は玄関脇のポーチライト用です。
台風で折れた栗の枝のうち、そこそこの太さで、そこそこの長さのものがもう無いので、少し短いものになってしまいました。

栗の枝は荒皮が厚いので、結構剥くのがめんどくさいです。
ヒノキの皮は結構簡単にぺろんと剥けたんですけど。
素人なりに、分かったことは、栗の皮は繊維方向に剥くより周方向の方が剥きやすそうなので、まず繊維方向に沿って筋のように剥いていきます。この時先端側から根元側の方へ剥いた方が若干ですが剥きやすそうに感じます。
筋のように剥いた後は円周方向に直角に剥いていきます。
そうすれば比較的簡単に向けます。

これで荒皮は剥けるのですが、さらに薄皮があるようです。この薄皮は空気に触れると?茶色く変色して見た目が汚くなりますし、これがまた剥きにくい。オービタルサンダーで磨いていく必要がありますが、剥きたては湿気ているので?綺麗に磨けません。しばらくおいてから磨いた方が良いようです。
以上他に栗を剥く人が居るとも思えませんが、自分への備忘録として・・。
夕方が訪れ、今日も良い感じに山が赤く染まります。

日が陰ってとても寒くなってきました。
今晩は冷え込みそうです。
Posted by ぶっち at
22:00
│Comments(0)